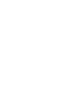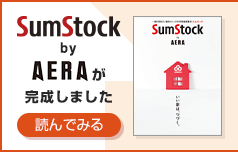中古住宅らぼ

※2025年3月17日現在の法律に準じた内容です。
長年放置された建物は、老朽化が進み、倒壊や火災のリスクが高まるだけでなく、近隣の景観や安全にも影響を及ぼし、近年では社会問題になっています。そのため自治体では、空き家の解体を促進することを目的にした補助金制度を設けているところが多くあります。ただし、補助金にはさまざまな種類があり、条件や手続きの流れも自治体によって異なります。
そこで本記事では、空き家解体の補助金制度について、補助金の種類や給付までの流れ、気をつけたいポイントを詳しく解説します。
空き家解体の補助金にはどんな種類がある?
空き家解体補助金の制度は自治体によってさまざまですが、ここでは空き家解体に利用できる代表的な補助金を紹介します。なお、同じ趣旨の補助金が自治体ごとに異なる名称で運営されていることもありますので、自治体のホームページで調べるときは「老朽家屋の解体補助」などのキーワードで検索してみてください。
老朽危険家屋解体撤去補助金
「老朽危険家屋解体撤去補助金」は、老朽化によって倒壊のおそれがある空き家の解体を促進する制度です。長い間使われず放置された家は、劣化が進みやすく、倒壊の危険性も高まります。こうした空き家を自治体が老朽危険家屋にあたるか調査を行い、解体が必要と判断された場合に解体費用の一部を補助する仕組みです。
補助金額は自治体によって異なり、解体費用の1/5~1/2程度が支給されることが一般的ですが、補助を受けるには条件があり、例えば所得制限が設けられている自治体もあります。まずは、お住まいの地域の窓口に問い合わせてみましょう。
建て替え建設費補助金
「建て替え建設費補助金」は、築年数が古く耐震性に問題がある建物を解体し、一定の基準を満たした建物を新しく建てる際に利用できる制度で、解体費用だけでなく、新しく建てる際の建築費の一部も補助されることが特徴です。老朽化した家は、地震などの災害時に倒壊のリスクが高まるため、安全な住まいへの建て替えを促すことを目的に支給されます。
自治体によって対象となる建物の条件や補助金額は異なりますので、あらかじめ確認を行うことが大切です。また、制度を利用するには、自治体の審査を受ける必要があります。まずは、お住まいの地域の窓口に問い合わせてみましょう。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」は、街の景観を守ることを目的とした解体に対して支給される制度です。老朽化した空き家を解体する際に、一定の条件を満たせば解体費用の一部が補助され、解体後は、地域の景観を形成する基準に沿った土地活用が求められます。
補助金額は、一般的に解体費用の1/5~1/2程度とされていますが、詳細な金額や条件は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。
自治体ごとの空き家解体の補助金
空き家解体に関する補助金の具体例を、自治体ごとに以下の表にまとめましたので参考にしてください。
ただし、あくまで例のため、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
※2025年3月17日時点での内容です。
| 地域 | 空き家解体の補助金制度 | 空き家解体の補助金額 |
| 東京都荒川区 | 古い空家の解体費助成 | 解体費用の2/3(上限100万円) |
| 神奈川県横浜市 | 住宅除却補助制度 | 以下のうち、もっとも低い額 ・20万円(課税世帯) ・40万円(非課税世帯) ・対象建築物の延べ面積(m2)×13,500円/m2に1/3を乗じた額 ・対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額 |
| 埼玉県行田市 | 老朽空き家等解体補助制度 | 解体費用の1/2以内(上限30万円) |
| 大阪府和泉市 | 老朽危険空家等除却補助金 | 対象家屋の除却に要する費用の80%(上限40万円) |
| 北海道札幌市 | 危険空家等除却補助制度 | (※通常型補助金の場合) 以下のうち、もっとも低い額 ・除却工事費×1/3 ・国が定める標準除却費(木造32,000円、非木造46,000円)×延べ面積×8/10 ・50万円 |
空き家解体の補助金が給付されるまでの流れ
空き家解体の補助金を受け取るには、申請から給付までいくつかの手続きが必要です。ここからは、空き家解体補助金を受け取るための手順を見ていきましょう。
補助金の交付申請
空き家解体の補助金を受けるには、一般的に工事を始める前に申請が必要です。もし申請前に解体を進めてしまうと、補助の対象外となるため注意しましょう。
また、補助金は年度ごとに受付期間が決まっており、予算が上限に達すると早めに締め切られることもあります。補助金の交付を申請する際には、自治体が指定する書類を準備する必要があるため、早めに自治体の窓口やホームページで詳細を確認し、交付申請を進めましょう。
自治体の審査
空き家解体の補助金を受け取るには、自治体の審査を通過することが必要です。審査では、建物の老朽度や周囲への影響などがチェックされ、解体の必要があるかどうか判断されます。また、書類の確認だけでなく、担当者が現地を訪れて調査を行うことが一般的で、すぐに結果が出るわけではありません。
通常は審査完了までに1カ月ほどかかり、申請が集中する時期は審査がさらに長引くことがあります。余裕を持ったスケジュールを立てて、早めに手続きを行いましょう。
解体工事
審査を通過すると交付決定通知が発行され、受け取った後に解体を始められます。空き家の解体を進める際は、市内の指定された解体業者を利用することが補助金の条件になっていることが一般的です。そのため、業者選びの際は、自治体のルールを確認し、対象になるかどうかチェックする必要があります。
また、解体工事には各種手続きが必要で、自治体への届け出や工事完了後の報告などを期限内に終わらせなければなりません。必要な申請は、解体業者が代行してくれることが一般的なので、信頼できる業者を選ぶことが大切です。工事前にスケジュールや手続きの流れを業者としっかり相談し、スムーズに解体を進めましょう。
補助金の請求
解体工事が終わると、一定の期間内に必要な書類をそろえて自治体へ完了報告を行うことが必要です。この審査を通過すると確定通知が発行され、補助金を受け取ることができます。手続きを円滑に進めるためには、解体業者と連携しながら、必要書類の準備を早めに行いましょう。
また、補助金は工事終了後に支給されるため、解体費用は一時的に全額自己負担となることに注意が必要です。手持ちの資金を用意しておかなければなりませんので、無理のない資金計画を立てましょう。
空き家を解体する際に気をつけておきたいポイント
ここでは、空き家解体の補助金を利用する場合の注意点など、空き家の解体にあたって事前に確認するべきポイントを解説します。
自治体によって補助金の条件が異なる
空き家解体の補助金は、全国の自治体で設けられていますが、制度の内容や条件は統一されていません。補助金の対象となる建物の基準や支給額、申請期限などは自治体ごとに異なるため、事前に詳しく確認することが大切です。また、自治体によっては補助金制度がない場合もあり、補助が受けられるかどうかを最初にチェックする必要があります。
さらに、「先着順」や「予算が上限に達した時点で終了」といった条件がある場合も多く、補助金の要件を満たしていても必ずしも補助を受けられるとは限りません。確実に補助金を活用するには、自治体のホームページで最新情報を確認し、早めに自治体に相談し申請することが重要になります。
対象となる工事内容は自治体によって異なる
空き家解体の補助金は、自治体ごとに対象となる工事の範囲が異なります。基本的に、建物本体の解体費用は補助対象となることが一般的ですが、ブロック塀の撤去や樹木の伐採、瓦礫の処分などが含まれるかどうかは自治体によってさまざまです。また、一部の自治体では、ブロック塀や庭木の撤去費用については、別の補助制度を設けていることもあります。
補助の対象がどこまでか分からない場合は、自治体の窓口やホームページで詳細を調べましょう。補助の範囲をしっかり確認しておくことで、想定よりも費用負担を軽くできる可能性があります。
税金の減免措置が受けられなくなる
空き家を解体すると、それまで適用されていた固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられなくなり、税負担が増えることになります。住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減されますが、建物を取り壊して更地にするとこの特例の適用外となるため注意が必要です。
また、空き家を放置しておき、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家等対策特別措置法)」による「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、自治体によっては強制的に減免措置の対象から除外される場合もあります。そのため、更地にした土地をどう活用するかもしっかり検討し、解体のタイミングを慎重に考えることが大切です。
空き家の活用方法
空き家の活用方法は、建物の状態などによって大きく分けて「解体して更地にする」か「解体せずに活用する」かの2つです。
更地にすると、駐車場などの用地として賃貸することができる、スムーズに売却しやすくなるなどのメリットがあります。ただし、解体費用がかかる上に、固定資産税の軽減措置がなくなる点には注意が必要です。
一方で建物を残す場合は、中古住宅として売却する、リフォームして賃貸に出す、カフェや店舗に改装するなどの方法があります。リフォームする場合には費用がかかりますが、工事の内容によっては自治体の補助金制度を活用できるケースもあります。
空き家をどのように活用するのがよいのか判断に迷ったら、不動産の専門家などに相談して、自分に合った活用方法を見つけましょう。
空き家解体の補助金が支給される条件

空き家解体補助金を受けるためには、自治体ごとに定められた条件を満たすことが必要です。ここでは、補助金が支給される一般的な条件を紹介します。
1年以上住んでいない
空き家解体の補助金を受ける際、多くの自治体では、1年以上住んでいないことを条件としています。これは、空家等対策特別措置法の基準に基づいており、人が暮らしておらず、長期間にわたり利用されていない住宅が対象です。具体的には、電気・ガス・水道といったライフラインが、長期間使われていない状態が該当します。
ただし、自治体によって条件に細かな違いがあるため、事前に窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。
新耐震基準を満たしていない
新耐震基準を満たしていないことも、空き家解体の補助金を受ける際の条件とされていることが多いです。現在の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に改正されており、それ以前に建てられた建物の多くは、現行の基準をクリアしていません。したがって、旧耐震基準で建てられた建物は、大きな地震の際に倒壊のリスクが高く、解体を促す目的で補助金の対象となる場合があります。
ただし、すべての既存(中古)住宅が補助を受けられるわけではなく、自治体によって具体的な条件が異なるため、事前に確認することが大切です。
老朽化しており倒壊リスクが高い
老朽化が進み、倒壊のリスクが高い空き家も、多くの自治体で解体補助金の対象となることが多いでしょう。長年放置された建物は、雨風の影響を受けて劣化しやすく、地震や台風などの災害時に崩れる危険性も高まるためです。
補助金を受けるには、自治体の調査を受ける必要があり、専門の担当者が現地で老朽化の度合いを確認します。その結果、危険な状態にあると判断されれば、補助金が適用される仕組みです。所有している空き家が老朽化している場合は、早めに自治体へ相談し、解体のタイミングを検討しましょう。
申請に必要な書類が整っている
補助金の申請には、申請書のほかにも必要とされる書類がいくつかあります。自治体によって異なりますが、次のような書類を求められることが多いです。
交付申請をするときの必要書類としては、解体計画書、解体工事の見積書、建物と土地の登記簿謄本、補助金の対象であることを証明するものなどがあります。
また、工事完了後に請求するときの必要書類としては、工事請負契約書、領収書、工事の内容や工事の完了を証明するものなどがあります。
スムーズに補助金を受け取るためには、必ず事前に必要となる書類を自治体に確認し、提出期限に余裕をもって指定された書類の準備を進めましょう。
まとめ
空き家を放置しておくとさまざまなリスクがあり、地域の安全や環境を守るためにも、適切な空き家対策を実施する必要があります。空き家の解体には、多くの自治体で解体費用の負担を軽くするための補助金制度が整備されています。そこで、補助金をうまく活用することによって、費用の負担を抑えて空き家の解体と解体後の土地の活用を進めることができます。
空き家を解体する際には、自治体ごとに異なる補助金の条件をしっかり確認することが大切です。申請前の調査や必要書類の準備、解体後の報告など、スムーズに手続きを進めるには事前の情報収集が欠かせません。
![一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会 [スムストック]](https://chukojutakulabo.sumstock.jp/wp-content/themes/sumstock/assets/img/header_logo.jpg)