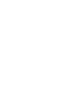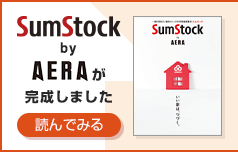中古住宅らぼ

※2025年9月19日現在の法律に準じた内容です。
2024年4月1日から、相続した家の不動産名義変更(相続登記)が義務化されました。この背景には、所有者がはっきりしない土地や建物が増えて、管理や活用がスムーズに行えないという社会問題があります。
「親が亡くなった後、手続きをいつまでにすればいいの?」と不安に思う方も多いでしょう。手続きを先延ばしにすると、法律上の罰則を受ける可能性があるだけでなく、将来的に相続人同士でトラブルになるリスクもあります。
本記事では、相続登記の期限や義務化の背景、手続きの流れ、必要書類、かかる費用について、初めてでも安心して進められるよう分かりやすく解説します。
相続した家の名義変更はいつまでに必要?
相続した家の名義を変更することを「相続登記」といいます。これまで相続登記は相続人の任意とされ、法的な義務とはされていなかったため、登記がなされないまま長期間放置されるケースが多く見られました。
しかし、今回の法改正によって相続登記は義務化され、一定の期限内に行わなければならなくなりました。
相続登記義務化の背景
相続登記が義務化された最大の背景は、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題です。
国土交通省の調査によると、日本全体の所有者不明の土地は九州の面積を上回るとされています(※)。所有者不明の土地は公共事業や都市開発、防災対策を進める上で大きな障害となってきました。
※出典:政府広報オンライン 相続登記が義務化!所有者不明土地を解消する不動産・相続の新ルールとは?
こうした背景から、不動産の権利関係を明確化する必要性が高まり、相続登記の義務化が決定されました。法律の施行により、所有者不明土地の拡大を抑制し、不動産の利活用を円滑に進めることが期待されています。
期限は相続開始から3年以内
相続登記は原則として「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に行うことが義務付けられています。通常は親など被相続人が亡くなった日がこれに該当します。
「3年」という期限は長いように見えますが、戸籍の収集や相続人同士の協議、必要書類の準備にはかなりの時間がかかります。相続人が多い場合や遠方にいる場合は、想像以上に日数を要しますので、余裕を持って取り組むことが大切です。
過去の相続にも適用される
今回の法改正の大きな特徴は、過去の相続にも遡って適用される点です。相続登記義務化の施行日である2024年4月1日を起点に3年以内の期限が設定されているため、2027年3月31日までに登記を行わなければなりません。
例えば、10年前に親が亡くなって名義変更をしていない不動産がある場合でも、2027年3月31日までに登記が必要になるのです。これまで「特に困っていないから」と手続きをしていなかった方も、今後は対応が必須となります。
放置していた不動産があるかどうか、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書を確認し、登記が済んでいない物件があれば早めに対処しましょう。
相続登記をせずに長期にわたって放置しておくと、相続人の一部が亡くなり次世代に権利が移ることで相続人が増えていき、全員の合意を得るのが困難になります。こうした事態を避けるためにも、できるだけ早く名義変更に着手することが重要です。
期限を過ぎた場合の罰則と不利益

相続登記の義務を怠った場合、単なる法律上のペナルティだけでなく、生活や資産管理において深刻な不利益が生じる可能性があります。
10万円以下の過料
正当な理由なく相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
過料は刑罰ではなく行政罰であり、前科がつくわけではありません。しかし、支払い義務は発生し、相続人にとって余計な金銭的負担となります。
相続登記を放置した場合の実務上の不利益
相続登記を放置することで発生する実務上の不利益は、過料以上に深刻です。
- 不動産を売却できない:名義が被相続人のままでは、買主に所有権を移転できず売却できません。
- 融資の担保にできない:銀行など金融機関は登記簿上の所有者を確認するため、名義変更していない不動産を担保にできません。
- 権利関係が複雑化する:相続人の一人が亡くなると、その子どもなどに権利が移ります。結果として相続人が雪だるま式に増え、合意形成が困難になります。
- 親族間のトラブル:修繕や固定資産税の負担を巡り「誰が払うのか」でもめるケースも多く見られます。
相続登記をせずに放置しておくと、登記手続きが困難な状態に陥ることもあります。その場合、家庭裁判所での調停や訴訟に発展する事例もあり、時間と費用の負担は計り知れません。
例外・猶予が認められるケース
遺産分割協議がまとまらず話し合いが続いているケースなど、正当な理由があれば過料の対象から外れます。
また、「相続人申告登記」という新しい制度も設けられています。これは、簡易な書類を法務局に提出して「自分が相続人である」という事実を申告し、登記義務を履行したものと見なす制度です。
相続人申告登記をしても所有権は移転せず名義は被相続人のままですが、申請義務を果たしたと見なされ、過料を避けられます。遺産分割協議が長引く場合の有効な対応策といえるでしょう。
相続した家の名義変更のおおまかな流れ

相続登記は、段階を追って進める必要があります。ここでは、相続登記の基本的なステップを解説します。
(1)相続人を確定する
最初に行うべきは、誰が相続人になるのかの確定です。相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、子ども・直系尊属(両親や祖父母)・兄弟姉妹の順に法定相続人が決まります。
確定作業には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集が必要です。出生からすべての転籍や結婚・離婚を経て死亡に至るまでの履歴を追わなければ、法定相続人を正確に確定できません。
この作業には時間がかかるため、できるだけ早く取りかかりましょう。本籍地が複数の自治体にまたがる場合、郵送請求を行う必要があり、1カ月以上かかることも珍しくありません。なお、戸籍証明書の広域交付制度を利用すると本籍地以外の市区町村窓口で請求することもできます。
(2)相続する財産を確認する
相続人が確定したら、次に行うのは相続財産の全体像を把握する作業です。財産には、不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
不動産については、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得すると、評価額を把握できます。この評価額は、後に登録免許税を計算する際にも必要となる資料です。
意外と見落としがちなのが「借金」や「保証契約」です。マイナスの財産も相続の対象となるため、プラスの財産より負債が大きい場合は、家庭裁判所での相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらは3カ月以内に手続きをしなければならないため、財産調査は速やかに行うことが求められます。
(3)誰が不動産を相続するのかを決定する
相続人と財産が確定したら、次は不動産を誰が相続するのかを決める作業です。
遺言書が存在する場合は、その内容に従って分配します。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、合意内容を遺産分割協議書として書面化する必要があります。法定相続どおりの分割であれば、原則として遺産分割協議書は不要ですが、後々のトラブルを防止するためにも作成しておくことが望ましいです。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要で、印鑑証明書を添付しなければなりません。一人でも欠けると無効になるため、遠方に相続人がいる場合や海外居住者がいる場合は、時間がかかる傾向があります。
(4)管轄の法務局へ登記を申請する
必要書類をそろえたら、最後に不動産所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。登記申請の方法には以下の3つがあります。
- 窓口申請:直接法務局に持参して提出する方法
- 郵送申請:書類を郵送する方法
- オンライン申請:インターネット経由で申請する方法
登記官による審査が行われ、問題がなければ登記簿上の名義が変更されます。完了には通常1~2週間程度かかりますが、案件の内容や混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。
なお、登記申請の手続きは複雑で手間がかかるため、司法書士に代行を依頼するのが一般的となっています。
相続登記にかかる費用
相続登記にはいくつかの費用がかかります。事前に目安を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
必要書類の取得にかかる費用
戸籍謄本、住民票、除籍謄本などの取得費用は、1通数百円程度です。被相続人の戸籍を出生から死亡まで連続してそろえると数十通に及ぶこともあり、その場合は合計で数万円の出費になることもあります。
また、相続人全員分の戸籍謄本なども必要となるため、人数が多いほど費用はかさみます。郵送請求の場合は別途送料も必要になるため、余裕を見て準備しておきましょう。
登録免許税
相続登記には、固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます。例えば、評価額が2,000万円の土地の場合は、8万円の登録免許税が必要です。土地と建物を相続する場合は、それぞれの評価額を合計し課税されます。
ただし、土地の評価額が100万円以下である場合や、すでに死亡している土地の相続人の登記を申請する場合など、一部のケースでは免税措置があります。こうした特例を利用できるかどうかは、法務局や司法書士に確認しておくと安心です。
司法書士報酬
司法書士に依頼する場合の報酬は、1件あたり数万円から十数万円が目安です。例えば、登記だけを依頼する場合は5~10万円程度ですが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も含めると20万円以上になるケースもあります。
費用はかかりますが、書類の不備や期限遅れを防ぎ、スムーズに登記を完了させる上で大きなメリットがあります。自分で対応するか、専門家に依頼するかは、時間と手間をどこまで負担できるかによって判断するとよいでしょう。
相続登記に必要な書類

相続登記には多数の書類が必要です。ここでは代表的なものを整理します。
| 書類 | 概要 |
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 出生から死亡までの記録を確認し、相続人を確定 |
| 被相続人の住民票の除票 | 死亡時の住所を確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人が存命であることを証明 |
| 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 不動産の詳細を確認 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税を算定 |
| 遺言書または遺産分割協議書 | 協議書は相続人全員の合意内容を示す書類 |
| 登記申請書 | 法務局での登記のための申請書 |
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
出生から死亡までの連続した戸籍で相続人を確定します。戸籍の収集には時間を要する場合があるため、早めに準備しましょう。取得先は本籍地の市区町村役場です。
被相続人の住民票の除票
被相続人の住民票の除票は、死亡時の住所を確認するためのもので、省略可能なケースもあります。取得先は住所地の市区町村役場です。
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本は、生存確認のためのものです。取得先は本籍地の市区町村役場です。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の詳細を確認するためのものです。オンラインで取得でき、現在の名義を確認できます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税の算出に使用します。管轄の市区町村役場で取得できます。
遺言書、または遺産分割協議書
自筆証書遺言による相続の場合は、法務局に保管されている場合を除いて検認済みの遺言書が必要です。遺産分割協議による相続の場合は、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書が必要です。
登記申請書
登記申請書は、登記のための申請書です。法務局指定の様式で作成します。
まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、相続開始から3年以内に行わなければなりません。期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があり、放置すると将来的に大きなトラブルに発展するおそれがあります。
初めて相続登記をする方にとっては、必要書類の多さや手続きの複雑さに戸惑うこともあるでしょう。そのような場合は、専門家である司法書士に相談するのが安心です。
また、相続した不動産の所有には、税金やメンテナンス費用の負担、空き家問題などのリスクが生じるため、状況によっては売却も検討することになります。相続した不動産が優良ストック住宅推進協議会に加盟している10社のハウスメーカーで建てられた住宅であれば、「スムストック」の基準を満たしている可能性もあります。相続後の売却の際に評価が高まり、有利に働くケースもありますので、建てたハウスメーカーに相談してみましょう。
相続登記は「早めの行動」が何より大切です。期限を意識し、計画的に進めていきましょう。
![一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会 [スムストック]](https://chukojutakulabo.sumstock.jp/wp-content/themes/sumstock/assets/img/header_logo.jpg)