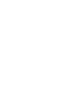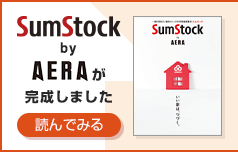中古住宅らぼ

※2025年6月9日現在の法律に準じた内容です。
「転勤が決まった」「親から家を相続した」など、ライフプランの変化をきっかけに、誰も住む予定のない持ち家をどう活用するか悩む方も多いのではないでしょうか。
そんな中、有効な選択肢の一つとして“賃貸に出す”ことを検討するケースが増えています。
持ち家を賃貸に出すことで、新たな収入源になるだけでなく、将来的に自分が再びその家に住む可能性を残せるといったメリットもあります。
とはいえ、いざ家を貸そうと思っても、「どんな手続きが必要?」「注意点は?」など、不安や疑問を感じる方も少なくありません。
そこで今回は、持ち家を賃貸に出す際のメリット・注意点・管理方法・コストについて、分かりやすく解説していきます。
家を貸すメリット
家を貸すことで得られるのは家賃収入だけではありません。空き家と比べ建物の劣化防止や防犯効果といったメリットもあります。
こうしたメリットを事前に把握しておくことで、「家を貸すべきかどうか」の判断もしやすくなるでしょう。
ここでは、家を貸すことによる主なメリットについて見ていきましょう。
家賃収入で安定した副収入(不動産所得)が得られる
家を貸すことで毎月の家賃収入が得られるため、住宅ローンを返済中の方であれば、その収入をローンの返済に充てることも可能です。
さらに、家賃収入を一定期間ためておけば、繰上返済に活用でき、返済期間の短縮や総返済額の軽減につながります。
また、貯金や資産運用、教育費、車の買い替え費用、海外旅行など、さまざまな用途に充てることもできます。
このように、毎月安定した副収入が得られ、家計にゆとりが生まれることは、家を貸す大きなメリットと言えるでしょう。
将来的に自分で住むこともできる
家を売却せずに貸し出すことで、将来的に自分が再び住むという選択肢を残せるのも大きなメリットです。
たとえば転勤などで一時的にその地域を離れる場合でも、暮らしやすく思い入れのある物件であれば、いずれ戻って住みたくなる可能性もあるでしょう。
売却してしまうと、同じような環境や条件の物件が再び見つかるとは限りません。
その点、家を貸すという選択をしておけば、ライフスタイルの変化や将来の状況に応じて柔軟に対応することができます。
劣化防止や防犯対策になる
家を賃貸に出さず放置していると空き家となり、定期的な換気や掃除が行われないことで建物の劣化が進みやすくなります。
さらに、不審者に狙われやすくなるなど、防犯面でのリスクも高まります。
また、家賃収入が得られないにもかかわらず、劣化を防ぐための修繕やメンテナンスに費用がかかる可能性もあるため、経済的な負担は決して小さくありません。
一方で、家を貸して誰かが住んでいれば、日常的な換気や掃除が行われることで建物や設備の状態を良好に保ちやすく、人の出入りがあることで防犯効果も期待できます。
家を貸す際の注意点
家を貸す注意点としては、空室による収入減、維持管理にかかるコスト、税金の負担に加え、希望するタイミングで自宅に戻れない可能性などが挙げられます。
また、住宅ローンを利用している家を賃貸に出す場合は、事前にローンを借り入れている金融機関から承諾を得る必要があります。
こうした注意点をあらかじめ理解することで、適切な資金計画やリスク対策を立てやすくなります。
借り手が見つからない「空室リスク」がある
家を貸す場合、すぐに借主が見つかるとは限らず、空室期間が長引く可能性もあり、その間は当然ながら家賃収入は得られず、実質0円となってしまいます。
特に、住宅ローンが残っている場合は、現在の住まいの費用に加えて、貸し出している家のローン返済も負担しなければならないため、家計に大きな影響を与える可能性があります。
こうしたリスクに備えるためにも、事前に空室リスクを想定した資金計画や対策を講じておくことが大切です。
維持・管理のコストが発生する
家を貸す場合、借主を見つけやすくするために必要に応じてリフォームやハウスクリーニング、設備修繕などを行うことがあります。
また、不動産会社に賃貸借の媒介を依頼する場合には、仲介手数料などの費用がかかります。
さらに、貸した後も経年劣化による修繕や設備のメンテナンスなど、家を維持するための費用が継続的に必要になる点にも注意が必要です。
※管理方法によっても負担は変わります。
自主管理の場合は、借主から要望や苦情があれば自ら対応しなければならず、手間や負担がかかります。
一方、管理委託の場合は、日々の運営からトラブル対応までの管理業務をすべてまたは一部委託することができますが、その分、管理手数料が発生します。
また、家を貸している場合でもあくまで所有権は貸主にあるため、固定資産税の支払い義務は継続します。これらの費用や負担をふまえた上で、無理のない資金計画を立てることが大切です。
家賃収入には税金がかかる場合がほとんど
家を貸して得られる家賃収入は、「不動産所得」として扱われます。利益が出た場合には、所得税(5~45%)や住民税(10%)の対象となり、給与所得など他の収入とあわせて確定申告が必要になります。
一方で、赤字(損失)が出た場合も、損益通算や繰越控除といった制度を利用するには、やはり確定申告が必要です。
※損益通算…不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の損失(赤字)を給与所得などほかの利益(黒字)と相殺して、課税される所得額を減らす制度
※繰越控除…損益通算してもその年に控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越して控除する制度(最長3年間)
特に初めて確定申告を行う場合は、準備や手続きに時間がかかることもあるため、余裕を持って進めることが大切です。
※参照:損益通算|国税庁
将来再び住む場合に希望のタイミングで住めない可能性がある
賃貸契約では、借地借家法によって借主の権利が保護されており、原則として貸主は正当な事由がないと途中解約や退去を求めることは認められていません。
そのため、転勤などから戻って元の家に住みたいと考えても、借主との契約状況によってはすぐに住めないケースもあります。
こうしたリスクを避ける方法のひとつが「定期借家契約」です。あらかじめ契約期間を定めておくことで、期間満了とともに確実に契約を終了できます。ただし、契約期間が短い場合は、通常の「普通借家契約」に比べて家賃が低くなる傾向があるため、注意が必要です。
家を貸す際にかかる費用と税金

家を貸す際には、仲介手数料や管理委託料、所得税など、さまざまな費用や税金が発生します。
どのような費用や税金がかかるのかを事前に把握しておくと、正確な資金計画を立てやすくなります。
ここでは、家を貸す際にかかる費用と税金について確認していきましょう。
【費用】仲介手数料や管理会社への手数料が必要
家を貸す際にかかる主な費用は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 仲介手数料 | 借主が決まった際に不動産会社に支払う手数料。原則として家賃の0.5カ月分。ただし借主の承諾のもと借主が家賃の1カ月分を負担するのも可。 |
| 管理委託手数料 | 貸した家の管理を委託する場合にかかる費用。相場は家賃の5~10%程度。 |
| ハウスクリーニング費用 | 費用は間取りやクリーニング箇所で異なる。 |
| 保険料 | 火災保険や施設賠償責任保険などの費用。金額は契約内容によって異なる。 |
| リフォーム費用 | 貸し出し前にリフォームを実施する場合は、その分の費用も負担が必要。 |
費用は業者や内容によって変わるため、早めに見積もりを取り、金額を把握しておくことが大事です。
【税金】固定資産税や家賃収入にかかる所得税が発生
家を貸す際にかかる主な税金は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 所得税 | 不動産所得には所得税がかかる。税率は課税所得金額に応じて5~45%の範囲で設定される。 |
| 住民税 | 不動産所得には住民税がかかる。所得割と均等割で構成され、所得割は税率10%、均等割は自治体で異なる。 |
| 固定資産税 | 毎年1月1日時点で不動産の所有者に対してかかる税金。税額は「課税標準額 × 税率(1.4%)」で算出される。また、不動産が市街地区域内にある場合は、都市計画税(税率は上限0.3%)もかかる。 |
※参照:所得税の税率|国税庁
家を貸すときの流れ
事前に家を貸す際の流れを把握しておくと、スムーズかつ計画的に進めることができます。
ここでは、家を貸すときの流れについて見ていきましょう。
1. まずは建てた会社と相談し、ケースに応じて複数社に賃料査定を依頼
まずは、建物について詳しく把握している、自宅を施工した建築会社の不動産部門や系列の不動産会社に相談しましょう。有利な条件で借り上げてくれる場合もあります。
また、必要に応じて、複数の不動産会社に賃料査定を依頼するのもおすすめです。
複数社で査定を行うことで、家賃の相場や管理サポートの内容を比較検討しやすくなります。
2.依頼する不動産会社を選ぶ
家賃やサポート内容に加えて、担当者の対応や口コミ・評判なども参考に不動産会社を選びます。
また、仲介手数料をはじめとした費用面についても事前にしっかり確認しておくことが大切です。
3.家を貸すための条件を決める
家賃や入居者の条件、賃貸期間(定期借家契約の場合)などについて、不動産会社と相談しながら決めていきます。
4.入居者を募集する
賃貸条件が決まったら、物件情報が不動産ポータルサイトや賃貸情報誌などに掲載され、入居者募集がスタートします。
入居希望者からの問い合わせ対応や内見の案内などは、基本的に不動産会社が行います。
5.賃貸借契約を結ぶ
入居者(借主)が決まったら、賃貸借契約を締結します。
契約手続きは基本的に不動産会社が対応します。
家賃の支払いについては、入居者から不動産会社(管理会社)へ振り込まれ、管理手数料などが差し引かれた金額が貸主に振り込まれるのが一般的です(管理委託やサブリース契約の場合)。
家を貸すときの管理方法は3種類
家を貸すときの管理方法には「管理委託」「サブリース」「自主管理」の3種類があります。
それぞれの特徴や違いを理解し、自分に合った管理方法を選ぶことが大切です。
ここでは、家を貸すときの3つの管理方法について見ていきましょう。
管理会社に依頼する「管理委託」
管理委託は、物件の管理や入居者対応を管理会社にすべて委託する方法です。
貸主は、家賃回収やトラブル対応などを自分で行う必要がないため、手間や労力を省けます。
ただし、毎月「管理委託手数料」が発生するため、事前に金額を確認しておくことが大切です。
不動産会社が借り上げる「サブリース」
サブリースは、不動産会社が物件を借り上げ、借主に転貸する方法です。
手数料は発生しますが、入居者の有無に関わらず毎月一定の家賃収入が得られるため、空室による収入減のリスクを抑えられます。
また、入居者対応や管理の手間を省けるのも特徴です。
自分で対応する「自主管理」
自主管理は、貸主自身が入居者対応や物件の管理業務をすべて行う方法です。
管理会社に支払う手数料が不要なためコストを抑えられるのが大きなメリットですが、トラブル対応や修繕手配などの負担が重くなる可能性もあり、時間や労力がかかる点には注意が必要です。
戸建てやマンションを貸すことで、家賃収入を得られるだけでなく、将来再び住む選択肢も残せるという大きなメリットがあります。
しかし一方で、空室による収入減や、維持管理にかかる費用、税金などの負担といった注意点もあります。
家を貸すかどうかを判断する際は、こうしたメリットや注意点の両方を理解しておくことが大事です。
まずは、不動産会社に相談し、現状に合った最適な選択肢を見つけましょう。
ライフプランや地域によっては、「賃貸」のほか「売却」も選択肢の一つ!
ここまで、持ち家を賃貸に出す際のポイントを紹介してきましたが「転勤から戻るかどうか分からない」「相続した家に誰も住む予定がない」「借り手が見つかりにくい地域にある」など、状況によっては、売却を選択肢に入れるのも一つの方法です。
例えば、住宅ローンを抱えている場合、賃貸に出している間も住宅ローンや固定資産税などのコストが継続して発生します。
一方で、売却すればこうした負担がなくなり、売却によって得た資金により資金的余裕が生まれることで、今後の選択肢も広がるでしょう。
将来の経済状況や物件、地域が賃貸に適しているかどうかによって「貸す」「売る」の判断基準は異なってきますが、最後に持ち家を売却するメリットや方法、流れについても簡単にご紹介します。
家を売却するメリットとは
家を売却するメリットは、以下のとおりです。
・住宅ローンの返済がなくなる
・固定資産税や修繕費などの維持管理コストが不要になる
・売却によってまとまった資金を得られる
・ライフスタイルの変化に柔軟に対応しやすくなる
・将来的な相続トラブルを回避しやすくなる
家を売却する方法
家を売却する方法には「仲介」「買取」「個人売買」など複数の選択肢があるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
まずは、自宅を施工した建築会社の不動産部門や、系列の不動産会社に相談してみましょう。
建物の構造や性能を熟知しているため、より具体的で役立つアドバイスを受けることができます。
家を売却する際の基本的な流れ
家を売却する際の基本的な流れは、次のとおりです。
1.不動産の査定を依頼する
2.不動産会社を選ぶ
3.媒介契約を結ぶ
4.売却活動を開始する
5.内見対応をする
6.売買契約を結ぶ
7.決済・引き渡しを行う
自宅を施工した建築会社の不動産部門などに相談し、売却を依頼する業者が決まったら、媒介契約を結びます。
契約後は、物件情報が「レインズ」や不動産ポータルサイトに掲載され、売却活動が始まります。
売却活動の中では内見対応が非常に重要なため、室内の掃除や見学スケジュールの調整に積極的に協力しましょう。
買主が決まれば、売買契約を締結し、代金の決済と家の引き渡しになります。
まとめ
家を貸すことで家賃収入を得られるなどのメリットがある一方で、維持管理の費用や手間がかかる、思いどおりのタイミングで再居住できないといった注意点もあります。
ライフプランや物件の立地によっては、家を貸すのではなく売却することも選択肢の一つです。
売却する場合は、まとまった資金が入り、住宅ローンの返済や維持管理の負担からも解放されます。
賃貸と売却の両方の査定を受ければ、どちらの選択肢も具体的に検討することができます。
さらに、「スムストック」かどうかの確認もあわせて行うことで、成約額のアップも見込めるので期待できるため、まずは査定を依頼してみましょう。
![一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会 [スムストック]](https://chukojutakulabo.sumstock.jp/wp-content/themes/sumstock/assets/img/header_logo.jpg)