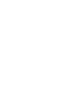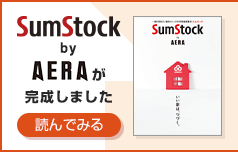中古住宅らぼ

※2025年6月9日現在の法律に準じた内容です。詳しくはお近くの税務署等にお尋ねください。
持ち家の売却を検討する際に「どれくらい税金がかかるの?」「節税対策にはどんな方法があるの?」といった不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
持ち家等の不動産を売却するとさまざまな税金が発生しますが、控除や特例を適切に活用することで納税額を抑えることができます。
一方で、控除や特例に関する知識がない場合は、本来払わなくてもいい税金を負担してしまうリスクがあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における節税対策について、実際のシミュレーションも交えて解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
家を売却する際に発生する税金の種類とタイミングは?
家を売却する際には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの税金が発生することがあります。
どの税金がいつ発生するのかを事前に把握しておくことは、スムーズな売却や適切な資金計画のためにも大切です。
ここでは、家を売却する際に発生する税金の種類とタイミングについて見ていきましょう。
課税文書にかかる「印紙税」
印紙税は、売買契約書や借用証書といった課税文書に課される税金のことです。
税額は契約金額に応じて異なり、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書、または請負に関する契約書については、軽減措置が適用されます。
税額の詳細は、以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
収入印紙を、課税文書に貼り付けて消印し、納付します。
登記の際に発生する「登録免許税」
登録免許税は、不動産の登記手続きの際にかかる税金です。
例えば、住宅ローンを利用している物件を売却する際には、金融機関が設定した抵当権を抹消するための抵当権抹消登記が必要です。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1件あたり1,000円(※土地と建物でそれぞれ1件とカウント)となっています。
なお、登記にはほかにも「住所変更登記」「氏名変更登記」「相続登記」などがあり、登記の内容や不動産の種類、固定資産税評価額などによって税額が異なります。
※参照:登録免許税の税額表|国税庁
売却益に対して課される「譲渡所得税」
譲渡所得税は、不動産を売却して出た利益(譲渡所得)に課される税金のことです。
この税金は、所得税・復興特別所得税・住民税で構成されており、売却する不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
具体的には、売却する不動産を5年超保有しているかどうかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分かれ、それぞれに異なる税率が適用されます。
なお、所有期間は不動産を売却した年の1月1日現在の期間において算定をいたします。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 39.63% (所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%) |
| 5年超(長期譲渡所得) | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) |
このように不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで、適用される税率には約2倍もの差があります。
なお、上記で紹介しただけでなく、住宅の売却にかかる税金はほかにもあります。
以下の記事で不動産を売却するとかかる税金や計算方法をさらに詳しく解説しているので、参考にしてください。
関連記事:不動産を売却するとかかる税金計算方法や利用できる控除を解説!
賢く活用したい!家を売却する際の税金対策

家を売却する際には、特例や制度を活用することで課税所得が抑えられ、所得税や住民税などの税負担を軽減することが可能です。
あらかじめ代表的な特例や制度を知っておくことで、自分の状況に合った制度を選択でき、より大きな節税効果が期待できます。
ここでは、家を売却する際に活用できる特例や制度について確認していきましょう。
控除額が大きい「3,000万円の特別控除」
家を売却する際に活用できる代表的な特例が「3,000万円の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」です。
この特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円までが控除されるため、税負担を軽減できます。
例えば、売却益が3,000万円以下の場合は、課税譲渡所得が0円になるため、譲渡所得税は発生しません。
3,000万円の特別控除を受けるには「現在その家に住んでいる」「転居している場合は3年目の年末までに売却する」「売却相手が親族や配偶者ではない」「過去2年以内にこの特例を利用していない」といった条件を満たす必要があります。
買い替え時に使える「買い替え特例」
家を買い替える際に利用できる「買い替え特例(特定のマイホームを買い換えたときの特例)」は、売却によって譲渡所得が発生しても、新しく購入した家を将来売却するまで課税を繰り延べできる制度です。
・売却金額よりも新しい家の購入金額が高い場合
→課税は新居を将来売却するまで繰り延べられる。
・売却金額よりも新しい家の購入金額が低い場合
→差額分は収入と見なされて譲渡所得の計算に用いられる。
特例を適用するには「令和7年12月31日までに売却する」「売却金額が1億円以下」といった条件を満たす必要があります。
ただし、「3,000万円の特別控除」と「買い換え特例」は併用できません。そのため、どちらを利用するかは、自身の状況や売却益の額、新しく住宅を購入する予定があるかどうかなどを踏まえて判断する必要があります。
たとえば、
●売却益が3,000万円以下で、買い替え予定がない場合
→ 「3,000万円の特別控除」が有利になるケースが多い。
●新しく住宅を購入する予定があり、売却益が大きい場合
→ 「買い換え特例」によって税の繰り延べを選ぶ方が適していることも。
判断に迷う場合は、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|国税庁
売却で損失が出た場合は「損益通算」
損益通算とは、持ち家を売却して損失(譲渡損失)が発生した際に、その損失をほかの土地や建物の譲渡所得と通算することで、課税される所得額を減らし、税負担を軽減できる制度です。
また、持ち家の場合、一定の要件を満たせば、分離課税の譲渡所得だけではなく、給与所得や事業所得など他の所得からも損益通算が可能です。
※参照:マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じたとき|国税庁
損益通算を行う場合には、確定申告が必要です。
※参照:損益通算|国税庁
相続した空き家を売却するなら「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続した空き家を売却する場合は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用することで、最大3,000万円の控除を受けられます。
この特例を活用すれば、課税される所得額を大幅に減らせるため、節税効果が期待できます。
適用を受けるには「昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること」「区分所有建物登記がされている建物でないこと」「相続開始直前まで被相続人のみが住んでいたこと」といった条件を満たすことが必要です。
※参照:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
10年超所有した家を売却するなら「10年超所有軽減税率の特例」
売却する持ち家の所有期間が10年を超えている場合は「10年超所有軽減税率の特例」を利用することで、譲渡所得に対する税率が軽減されます。
通常、所有期間が5年を超える場合の税率は、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の合計20.315%です。
しかし、所有期間が10年を超えており、この特例が適用される場合は、譲渡所得のうち6,000万円までの部分については、所得税(復興特別所得税含む)が10.21%、住民税が4%の合計14.21%となります。
売却の際の税金をシミュレーション付きで解説!
譲渡所得税の計算方法を理解しておくと、早い段階で税額のシミュレーションができ、資金計画を立てやすくなります。
ここでは、譲渡所得税の計算手順とシミュレーションを紹介します。
1.譲渡所得を計算する
まずは、譲渡所得を計算します。
譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
※取得費…家を購入したときにかかる費用(購入価格や仲介手数料、不動産取得税など)
※譲渡費用…家を売却したときにかかる費用(仲介手数料や印紙税など)
※建物の取得費は減価償却費相当額を考慮して計算します。
2.特別控除を差し引き課税譲渡所得を求める
譲渡所得を求めたら、次に課税譲渡所得を計算します。
課税譲渡所得は、以下の計算方法で求められます。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 特別控除額
例えば「3,000万円の特別控除」が適用される場合は、譲渡所得から3,000万円を差し引いた金額が課税譲渡所得となります。
3.税率をかけて譲渡所得税を算出する
課税譲渡所得を求めたら、譲渡所得税を算出します。
譲渡所得税は、以下の計算方法で求められます。
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
税率は、不動産の所有期間に応じて異なります。
- 所有期間が5年以下の場合: 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
- 所有期間が5年を超える場合: 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
次に、譲渡所得税のシミュレーションを2つのケースで紹介します。
具体例①
4,000万円で購入したマイホームを3,000万円で売却したケース
<シミュレーション条件>
・取得費:4200万円
・譲渡費用:150万円
※ここでは取得費の減価償却は考慮しません。
このケースでは、譲渡所得は「売却価格3,000万円 −取得費 4,200万円 −譲渡費用150万円 = 0円」となり、譲渡所得がマイナスなので課税譲渡所得も0円となるため、譲渡所得税は発生しません。
具体例②
購入額不明(相続した家)を4,000万円で売却したケース
<シミュレーション条件>
・取得費:不明
・譲渡費用:150万円
・特例:3,000万円の特別控除
・所有期間:10年
※ここでは取得費の減価償却は考慮しません。
相続した不動産などで取得費が不明な場合は売却価格の5%(4,000万円×5%=200万円)を取得費として概算します。
そのため、このケースでの譲渡所得は「売却価格4,000万円 −取得費200万円 −譲渡費用 150万円 = 3,650万円」となります。
また、ここから3,000万円の特別控除を差し引き、課税譲渡所得は「3,650万円 − 3,000万円 = 650万円」です。
不動産の所有期間は5年を超えているため税率は20.315%となり、譲渡所得税は「650万円 × 20.315% = 132万475円」となります。
もし、特例控除を適用できない場合は、譲渡所得税は「3,650万円 × 20.315% = 741万4,975円」となり、税負担は大幅に増加します。
なお、空き家特例を使用する場合、所有期間10年超の軽減税率の適用はありませんのでご注意ください。
※参照:取得費が分からないとき|国税庁
家を売却する際の注意点
家を売却する際の注意点には、特例控除が住宅ローン控除と併用できないケースがあることや、税金ごとに納付方法や支払い時期が異なることなど注意すべきポイントがあります。
ここでは、家を売却する際の注意点について見ていきましょう。
確定申告が必要になることがある
家を売却する際には、状況によっては確定申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。
具体的には、次のようなケースで確定申告が必要になります。
・売却によって利益が出て譲渡所得税が発生する場合
・3,000万円の特別控除などの特例を適用する場合
・損失が発生して損益通算や繰越控除を利用する場合
確定申告が必要な場合は、期間内に申告手続きと所得税の納付を行う必要があります。
例えば、令和6年分の確定申告は、令和7年2月17日~3月17日までが申告期間となります。
※参照:【確定申告・還付申告】|国税庁
住宅ローン控除との併用はできない場合がある
家を売却する際は、住宅ローン控除と各種特例控除を併用できないなどの制約があるため、注意が必要です。
住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を最長13年間にわたり、所得税や一部の住民税から控除できる制度です。
ただし「3,000万円の特別控除」や「買い替え特例」といった特例と、住宅ローン控除を同時に利用することはできません。
そのため、特例の適用を検討する際は、住宅ローン控除と比較してどちらの節税効果が高いかをシミュレーションして、慎重に判断することが大切です。
不動産の所有期間によって税率が変わる
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年を超える場合は20.315%と税率に約2倍の差があります。
そのため、売却を検討している物件の所有期間が5年以下の場合は、すぐに売却すべきか、5年を超えてから売却したほうがよいのか、シミュレーションをして判断することが大切です。税率の差が大きいため、タイミングを見極めることが節税のポイントとなります。
税金の納付方法やタイミングは異なる
家を売却する際には、譲渡所得税(所得税、復興特別所得税、住民税)や印紙税、登録免許税などの税金が発生することがあります。
それぞれ納付方法や支払いのタイミングが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
主な税金と納付タイミング・方法は、次のとおりです。
| 税金 | 納付のタイミングと方法 |
| 所得税 復興特別所得税 | 家を売却した年の翌年の確定申告期間に納付が必要。振替やインターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリなどで納付が可能 |
| 住民税 | 売却した翌年の6月以降「給与からの毎月天引き(特別徴収)」または「年4回に分けて納付または一括での納付(普通徴収)」のいずれかの方法で支払う |
| 印紙税 | 課税文書に印紙を貼り消印することで納付する |
| 登録免許税 | 金融機関や郵便局で現金で納付し、領収書を申請書に貼付して法務局に提出する。また、印紙やキャッシュレスによる納付も可能。 |
※参照:【税金の納付】|国税庁
取得費が不明な場合は売却額の5%で計算する
譲渡所得税の計算では家の取得費が必要になりますが、建物が古かったり相続で引き継いだりした場合は、正確な取得費が分からないこともあります。
取得費が不明な場合は、売却金額の5%を概算取得費として計算することが認められています。
※参照:取得費が分からないとき|国税庁
まとめ
家を売却する際には、譲渡所得税や登録免許税、印紙税など、さまざまな税金が発生する可能性があります。
特に注意が必要なのは、売却益が出た場合だけでなく、特例を利用する場合や、損失が発生して損益通算や繰越控除を行う場合も確定申告が必要になるという点です。
家の売却を検討し始めたら、まずは自宅を建てたハウスメーカーに相談するのも有効な選択肢です。
特定のハウスメーカーで建てた物件は「スムストック」という優良戸建て物件に認定されることがあり、売却価格が高く評価される可能性があります。
自宅がスムストックに該当するか気になる方は、一度チェックしてみるとよいでしょう。
![一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会 [スムストック]](https://chukojutakulabo.sumstock.jp/wp-content/themes/sumstock/assets/img/header_logo.jpg)