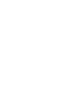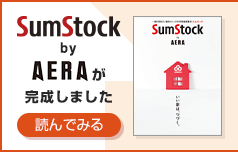中古住宅らぼ

※2025年8月20日現在の法律に準じた内容です。詳しくはお近くの税務署等にお尋ねください。
不動産を売却した後は、確定申告が必要になる場合があります。初めての売却では、手続きの内容や必要書類が分からず、不安を感じる方もいるかもしれません。
確定申告の意味や流れを正しく理解していないと、申告期限に間に合わず、延滞税や加算税といったペナルティが発生するおそれがあります。
本記事では、不動産売却後に確定申告が必要となるケースや、必要書類、申告の流れ、注意点までを分かりやすく解説します。申告ミスを防ぎ、安心して手続きを進めるための参考にしてください。
不動産売却で確定申告が必要になるケースとは?
不動産を売却した場合でも、必ず確定申告が必要になるというわけではありません。確定申告が必要となる主なケースは、以下の3つです。
① 譲渡所得(利益)が発生する場合
不動産の売却によって譲渡所得、つまり売却益が発生した場合は、確定申告が必要です。譲渡所得とは、売却価格から取得費(不動産の購入代金)と譲渡費用(売却時にかかった費用)を差し引いた金額を指します。譲渡所得は以下の式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得に対しては、所得税・住民税が課税されます。税率は、不動産の所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と区分され、それぞれ異なる税率が適用されます。
譲渡所得についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
不動産を売却するとかかる税金計算方法や利用できる控除を解説!
② 譲渡損失(売却損)が出て損益通算や繰越控除をしたい場合
不動産を売却して譲渡損失、つまり売却損が出た場合、税金はかからないため原則として確定申告は必要ありません。ただし、一定の条件を満たすと、「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用できます。この特例を受けるためには、確定申告が必要になります。
損益通算とは、不動産売却で生じた損失を給与所得・事業所得などほかの所得から差し引く仕組みで、課税所得全体を減らす制度です。これにより、所得税や住民税の負担を軽減できます。
繰越控除とは、損益通算で引き切れなかった損失を、最長3年間、翌年以降の所得から差し引ける制度です。
特例を受けるためには、以下の条件が求められます。
- 実際に自分が住んでいた家屋であること
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
- 親族など特別関係者との売買ではないこと
- 新居は売却した年の前年から翌年までの間に購入し、床面積は50m2以上であること など
特例の適用条件については、国税庁のWebサイトなどで詳細を確認するようにしてください。
③ 3,000万円特別控除などの特例を受ける場合
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の特例を適用できます。この特例を適用すると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されるため、課税所得額が大幅に減少し、場合によっては税金が非課税になります。
特例の適用を受けるためには、確定申告が必須となります。申告を忘れてしまうと、特例を受けられませんので注意してください。
不動産売却で確定申告する際の必要書類

不動産売却の確定申告では、さまざまな書類の準備が必要です。ここでは、主な必要書類とその内容を解説します。
確定申告書第一表・第二表
確定申告書第一表と第二表は、確定申告のメインとなる書類です。第一表には収入金額や所得金額、所得控除額、納税額などを記載し、第二表には所得の内訳や社会保険料控除などの詳細を記載します。これらの書類は、税務署の窓口や国税庁のWebサイトから取得できます。
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産売却による譲渡所得は、ほかの所得と分けて税額を計算する「分離課税」の対象となります。そのため、通常の確定申告書とは別に、確定申告書第三表(分離課税用)の作成が必要です。
この書類には、譲渡所得の金額やそこから発生する税金などを記載します。確定申告書第一表・第二表と同様に、税務署の窓口や国税庁のWebサイトで取得可能です。
購入時・売却時の売買契約書(写し)
不動産の購入時と売却時の売買契約書のコピーが必要です。これらの契約書には、不動産の取得価格や売却価格、契約日などが明記されており、譲渡所得を計算する際の重要な資料となります。
確定申告書と一緒に提出する必要はありませんが、税務署から提示を求められる場合があるため、大切に保管しておきましょう。
譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書には、不動産売却における譲渡所得金額の詳細を記載します。売却物件の情報や取得時の情報、特別控除の適用などを記入し、譲渡所得の計算を行います。
内訳書の内容をもとに、確定申告書第三表を作成します。譲渡所得の内訳書は、国税庁のWebサイトからダウンロードして取得できます。
取得費・譲渡費用を確認できる書類
譲渡所得を計算する際には、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引きます。これらの費用を証明するために、関連する領収書や明細書を準備する必要があります。
取得費に含まれる主な費用は以下のとおりです。
- 不動産の購入代金
- 購入時の仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
- 不動産取得税
- 購入後にかかったリフォーム費用
譲渡費用に含まれる主な費用は以下のとおりです。
- 売却時の仲介手数料
- 印紙税
- 測量費
- 建物を取り壊した場合はその費用
- 売却のために行ったリフォーム費用
これらの書類は確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあった際に提示を求められる可能性があるため、しっかりと保管しておきましょう。
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所在地や種類、面積、所有者などの登記情報が記録された公的な書類です。売却した不動産の正確な情報を確認するために必要となります。
管轄の法務局で取得できるほか、オンラインでの請求も可能です。取得には手数料がかかります。
本人確認書類
確定申告書を提出する際には、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードのみで本人確認が可能です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが記載された書類(通知カードなど)と、運転免許証や健康保険証などの身分証明書の両方が必要になります。
なお、e-Tax(電子申告)を利用する場合は、本人確認書類の提出は不要です。
不動産売却で確定申告する際の進め方

不動産売却後の確定申告は、以下のステップで進めていきます。
1.確定申告の必要書類を準備する
まずは、上記で紹介した確定申告の必要書類をすべて準備しましょう。譲渡所得が発生する場合や損益通算・特別控除を利用する場合には、確定申告が必須となりますので、早めに書類の準備を始めることが重要です。過去の購入時の書類が手元にないケースもあるため、時間に余裕をもって進めましょう。
2.譲渡所得の内訳書を作成する
必要書類がそろったら、譲渡所得の内訳書を作成します。この書類には、売却した物件の情報や購入時の情報、取得費や譲渡費用などを記載し、譲渡所得の金額を計算します。
また、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、その旨も忘れずに記載してください。内訳書を正確に作成することで、後の確定申告書の作成がスムーズになります。
3.確定申告書を作成する
譲渡所得の内訳書が完成したら、その内容をもとに確定申告書第三表、そして確定申告書第一表・第二表を作成します。
確定申告書の作成は、国税庁のWebサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。画面の指示に従って情報を入力していけば、自動で計算が行われ、間違いなく作成できます。
不明な点があれば、税務署の相談窓口や税理士に相談するようにしましょう。
4.確定申告書と添付書類を税務署に提出する
作成した確定申告書と添付書類は、管轄の税務署に提出します。提出方法は、①税務署の窓口へ直接持参する、②郵送する、③e-Tax(電子申告)を利用する、のいずれかです。
①税務署の窓口へ持参
直接提出できるため、不明点があればその場で質問できます。
②郵送
遠方の場合や忙しい場合に便利です。申告期限に間に合うよう、余裕をもって郵送するようにします。
③e-Tax(電子申告)
自宅のパソコンやスマートフォンから申告できるため、もっとも手軽な方法です。ただし、事前に「利用者識別番号」の取得や、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーなどが必要になる場合があります。確定申告が初めての方は、早めに準備を進めておく必要があります。
いずれの方法でも、申告期限(通常は売却翌年の3月15日)までに提出するよう注意しましょう。土日祝にあたる場合は、次の平日が期限になります。
5.納税または税金の還付を受ける
譲渡所得税が発生する場合は、申告期間内に納税を済ませる必要があります。納税方法は、税務署や金融機関の窓口での現金納付、コンビニエンスストアでの納付(一定額以下の場合)、インターネットバンキングによる電子納税、または振替納税などがあります。
一方、特例の適用などで税金が還付される場合は、確定申告からおよそ1カ月から1カ月半程度で、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
不動産売却で確定申告する際の注意点

不動産売却の確定申告では、いくつかの重要な注意点があります。これらを押さえておくことで、スムーズに手続きを進め、予期せぬトラブルを避けることができます。
申告・納税の期限は必ず守る(通常は翌年3月15日まで)
不動産売却による譲渡所得の確定申告期間は、原則として売却した年の翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に、確定申告書の提出と所得税の納付を済ませる必要があります。土日祝日が重なる場合は、翌営業日が期限となります。
初めての確定申告の場合、必要書類の準備や確定申告書の作成に予想以上に時間がかかることがあります。申告期限直前になって慌てないよう、売却後すぐに準備に取りかかることを強くおすすめします。
特例の適用条件は事前にチェックする(3,000万円特別控除の要件など)
前述のとおり、マイホーム売却時の3,000万円特別控除など、不動産売却には税負担を軽減できるさまざまな特例があります。
しかし、それぞれの特例には適用条件が細かく定められています。例えば、3,000万円特別控除の場合、主な適用条件は以下のとおりです。
- 自分が住んでいた家屋とその敷地を売却すること(別荘等、娯楽保養目的ではないこと)
- 売却した年の前々年、前年、または売却した年のいずれかの年に、ほかのマイホームを売却してこの特例の適用を受けていないこと(買替えや交換の特例も含む)
- 災害によってマイホームが滅失した場合、その敷地を売却したときは、その日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 親子や夫婦等、特別な関係の人物に対する譲渡ではないこと
これらの条件を満たしているかどうか、事前にしっかりと確認します。不明な点があれば、税務署や税理士に相談しましょう。
経費として認められる費用を把握する(仲介手数料・測量費など)
不動産売却にかかる税金を計算する際、取得費や譲渡費用として計上できる費用が多いほど、課税対象となる譲渡所得が減り、その結果、税金の負担を軽くできます。
これらの費用については、税務署から問い合わせを受けた際に証明する必要があるため、領収書や明細書などの証拠書類は必ず保管しておきましょう。
特に、購入から年数が経っている場合は、当時の書類を紛失しているケースも少なくありません。その際は、売主、不動産仲介会社、リフォーム会社などに問い合わせ、再発行やコピーが可能かどうかを確認しましょう。
申告の遅れ・漏れには罰則がある(延滞税・無申告加算税の可能性)
確定申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告を行わなかったり、申告内容に誤りがあったりした場合は、ペナルティが課せられる可能性があります。
【確定申告を期限内に行わなかった場合】
無申告加算税が課せられます。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%の割合で加算されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は、加算税率が5%に軽減されます。
【納付期限までに税金を納めなかった場合】
延滞税が課せられます。延滞した期間に応じて、定められた割合の税金が加算されます。税率は期間によって異なりますが、年率で数%から10%を超える場合もあります。
事実を仮装・隠蔽して申告した場合や無申告の場合には、重加算税が課せられます。通常の加算税に代わって課せられる非常に重いペナルティです。無申告の場合は原則40%、過少申告の場合は原則35%の税率が適用されます。
こうしたペナルティを避けるためにも、確定申告を正しく理解し、期限内に正確な申告を行うことが大切です。
まとめ
不動産を売却して利益が出た場合や、損益通算・繰越控除などの特例を適用したい場合には、確定申告が必要です。
また、優良な既存住宅として認定された「スムストック」に該当するかどうかも、査定段階で確認しておきましょう。
スムストックの住宅は各種書類がしっかりと残っているため、売却活動から確定申告までの手続きがスムーズです。そのため、売主・買主の双方が安心して取引できることで売却時の信頼性が高まり、よりよい条件での売却が期待できます。
まずは、気軽に建てた会社に査定依頼をして現在の状況を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
![一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会 [スムストック]](https://chukojutakulabo.sumstock.jp/wp-content/themes/sumstock/assets/img/header_logo.jpg)